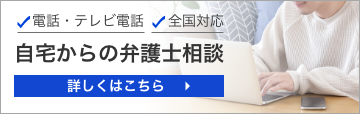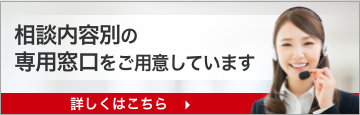未払い残業代を請求されたらどうする? 従業員への対応を弁護士が解説
- 労働問題
- 未払い残業代
- 請求されたら
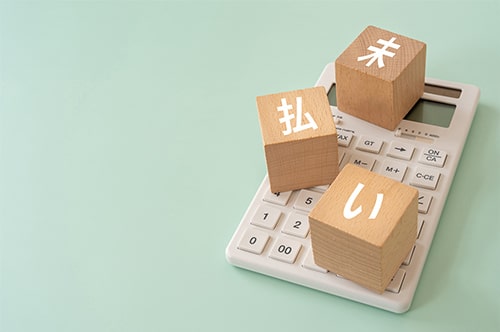
福島労働局が公表している令和5年度の「個別労働紛争解決制度の実施状況」によれば、福島労働局への総合労働相談件数は1万6053件で、11年連続で1万5000件を超える状況が続いています。
中でも、未払い残業代の問題は、会社と従業員の間で争いが発生しやすいトラブルのひとつです。「元従業員から未払いの残業代があるとして内容証明郵便が届いた」「未払い残業代があると労働基準監督署に通報された」という場合、会社としてはどのように対応すればいいのでしょうか。
この記事では、未払い残業代を請求された場合の対応方法や、未払い残業代に関する判例、未払い残業代を請求された際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの弁護士が解説していきます。
1、未払い残業代を請求されたらどうする?
従業員や元従業員から未払いの残業代を請求された場合、言われるがまま支払いに応じる必要はありません。まずは、要求の内容が正しいかどうか、事実を精査することから始めましょう。
ここでは、未払いの残業代を請求された場合の対処法について解説していきます。
-
(1)従業員の主張を確認する
従業員や元従業員から未払いの残業代を請求された場合、まずはその従業員の主張を確認する必要があります。そもそも従業員が主張している残業時間や残業代の計算方法は、合理的なものでしょうか。
たとえば、従業員が主張している時間計算が誤っている場合には、未払いの残業代は発生していない可能性があります。残業が行われていたとしても、雇用契約どおり固定残業代やみなし残業手当として固定残業手当を支給している場合には、未払いの残業代は発生していないことになります。
また、従業員が、労働条件や労務管理に関して、経営者と一体的な立場にある人(管理監督者)にあたる場合は、残業代を支払う必要はありません。 -
(2)未払い残業代があった場合は残業代を計算する
未払いの残業代が発生していることがわかった場合には、会社側でも残業代を計算する必要があります。未払いが発生しているからといって、従業員の請求どおりに金額の支払いに応じるのではなく、会社としても未払いとなっている正確な金額を計算してください。
まずは、会社が持っている雇用契約書、就業規則・賃金規程、勤怠管理表などの資料と照らし合わせて、従業員の労働時間はどのくらいで、賃金はいくらになるのか、そのうち未払いがどれくらいになるのかなど、客観的な事実を確認しましょう。 -
(3)従業員と話し合う
会社としての立場が固まった段階で、当該従業員と話し合いを行いましょう。
証拠に基づき従業員からの残業代請求が適正ではない場合には、そのまま飲むのではなく適切に反論するべきです。当事者間が話し合いによる解決を望んでいる場合には、早期にトラブルを解決できる可能性があります。
すでに退職している従業員の場合には、書面でのやり取りになるケースは少なくありません。相手方に代理人弁護士がついている場合には、その弁護士とやり取りをして話し合いを進めることになります。 -
(4)労働基準監督署からの通知に対応する
未払いの残業代がある場合、従業員から労働基準監督署(労基署)に通報されることもあります。労基署から調査を受け、発行された「是正勧告」に従わない場合は、ペナルティーを受ける可能性があり注意が必要です。
労働基準監督署の調査では、関係帳簿の確認や、事業所の責任者や担当者などに聞き取り調査が行われることになります。調査の結果、労働基準法に違反していることが判明した場合には、是正勧告書が出されます。
企業側は是正勧告書に指定された期限までに改善措置を講じて、労基署に是正報告書を提出しなければなりません。労基署の勧告自体には罰則はありませんが、適切な改善が見られない場合には、会社名が公表され、評判が悪化することも考えられます。
なお、賃金の未払いは、労働基準法違反です(労働基準法第24条)。「6か月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」が科されるおそれがあります。刑罰は、会社の経営者である事業主のみならず、業務命令や指揮監督をする権限がある人にも適用される可能性があります。 -
(5)話し合いがまとまらない場合は労働審判、訴訟へ移行する
従業員との話し合いがまとまらない場合には、労働審判や訴訟など裁判手続きに移行する必要があります。
労働審判手続とは、会社と従業員の間で生じた労働紛争を解決するために、労働審判委員会に判断を求める手続きです。労働審判手続では、裁判官1名と労働問題に対する知識や経験を有する労働審判員2名が当事者の間に入り、まずは話し合いを行います。
話し合い(調停)による解決が図れない場合は、労働審判委員会が判断する「労働審判」が行われます。
労働審判に不服のある当事者は、異議申立てが可能です。これにより、訴訟に移行することができます。訴訟では、最終的には裁判所が判決で請求の可否を判断することになります。
2、未払い残業代を請求された場合の注意点
会社が従業員から未払い残業代を請求された場合、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。
ここでは会社側の注意点について解説していきます。
-
(1)従業員に不利益な扱いとならないようにする
まず、未払い残業代を請求した従業員に対して不利益な取り扱いをしてはいけません。
未払いの残業代を請求することは労働者として正当な権利であるため、そのことを理由として配置転換・降格・減給・解雇など不利益な取り扱いをすることは法律で禁じられています。 -
(2)時効が成立しているか確認する
残業代請求権には消滅時効があります。令和2年4月1日以降に発生した未払い残業代の請求権は、給料日の翌日から3年が経過することで消滅します。
すでに時効が成立している未払いの残業代については、会社側が時効成立の主張(時効の援用)をすることで、支払い義務を免れることになります。 -
(3)従業員が管理監督者に該当するか確認する
従業員が管理監督者である場合、労働時間に関する規定が適用除外されています。
そのため、会社は管理監督者である従業員に対しては時間外労働の割増賃金を支払う必要がありません。ただし、管理監督者であっても深夜手当(午後10時~午前5時までの労働への割増賃金)は支払う必要があります。
また、役職名が管理職であっても、実態として人事権や労働時間の裁量がないなど、実質的な管理監督者としての権限や責任を持たない「名ばかり管理職」の場合は、割増賃金の適用除外とはならないことに注意が必要です。
従業員が実態として管理監督者に該当するか、裁量や業務内容を確認しましょう。
3、未払い残業代に関する判例・裁判例
訴訟された場合、未払いの残業代に関して、裁判所はどのような判決を下すことがあるのでしょうか。
ここでは、未払い残業代が争われた事件において、会社の反論が認められなかった判例と、認められた裁判例をご紹介します。
-
(1)会社側が敗訴した判例:阪急トラベルサポート事件
【事案の概要】
従業員Xは、A会社が企画する海外ツアーごとに添乗員を派遣するY社に雇用されていました。Xには日当が支払われていましたが、時間外労働や休日労働に対する残業代の未払いがあるとして、その支払いを求めてY社を訴えました。
これに対して、Y社は、事業場外労働(会社の指揮命令下に置かれていない場所で業務に従事すること)における「みなし労働時間制」が適用されると主張しました。
【裁判所の判断】
最高裁判所は、以下のとおり、従業員の裁量が小さいことを理由に、みなし労働時間制の適用を否定しました。本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている
(中略)
業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない
(最高裁判所 平成26年1月24日判決)
-
(2)会社側が一部勝訴した裁判例:姪浜タクシー事件
【事案の概要】
Y社は、タクシーによる旅客運送事業を行う会社です。XはY社の営業次長として勤務していました。Xは、平成11年にタクシーの乗務員として雇用されたものの、その翌年には営業職に配置転換され、平成16年にY社を退職。Xは、時間外労働・深夜労働の割増賃金および退職金規定変更前の金額との差額の支払いを求めてY社を訴えました。
これに対して、Y社は、Xがいわゆる管理監督者に該当するため時間外手当は発生しないと反論しました。
【裁判所の判断】
裁判所は、次のとおり、多数の乗務員を直接に指導・監督する立場にあり、出退勤時間についても特段の制限を受けていなかったこと、そして他の従業員に比べ高額の報酬を得ていたことなどから、Xが管理監督者に該当することを理由に時間外手当の請求を認めませんでした。
ただし、深夜労働の割増賃金請求と退職金規定変更の無効性については労働者側の主張が一部認められています。原告は、営業部次長として、終業点呼や出庫点呼等を通じて、多数の乗務員を直接に指導・監督する立場にあったと認められる。また、乗務員の募集についても、面接に携わってその採否に重要な役割を果たしており、出退勤時間についても、多忙なために自由になる時間は少なかったと認められるものの、唯一の上司というべきB専務から何らの指示を受けておらず、会社への連絡だけで出先から帰宅することができる状況にあったなど、特段の制限を受けていたとは認められない。さらに、他の従業員に比べ、基本給及び役務給を含めて700万円余の高額の報酬を得ていたのであり、被告の従業員の中で最高額であったものである。加えて、原告が被告の取締役や主要な従業員の出席する経営協議会のメンバーであったことや、B専務に代わり、被告の代表として会議等へ出席していたことなどの付随的な事情も認められ、これらを総合考慮すれば、原告は、いわゆる管理監督者に該当すると認めるのが相当である
(福岡地方裁判所 平成19年4月26日判決)
4、従業員との労働トラブルを弁護士に相談するメリット
従業員との労働トラブルについては、法律や複雑な手続きが関係するため、企業の人事・総務担当者だけでは対応が難しいことが多いでしょう。
ここでは、労働トラブルを弁護士に相談する3つのメリットについて解説していきます。
-
(1)従業員との交渉を任せられる
まず、弁護士に依頼することで、従業員との話し合いや交渉を任せておくことができます。
弁護士に任せておけば、相手方の主張の正当性や、会社側として反論すべき事実についても、対応してもらえます。
相手方との交渉を弁護士に代行してもらうことで、早期に紛争が解決できる可能性が高まります。 -
(2)裁判に発展した場合でも法的な手続きをお願いできる
従業員との話し合いでは解決できず、労働審判や訴訟などの裁判手続きに発展した場合であっても、弁護士であれば引き続き対応を任せられます。
会社側に有利な事実の主張や証拠の提出など必要な手続きについても、すべて弁護士に一任できるので、対応する社員の負担を下げ、通常業務への影響を極力少なくすることが可能です。 -
(3)トラブルが大きくなる可能性を低くできる
労使間で直接話し合いをすると、感情的な対立が生じたり、誤った法的判断に基づく主張の応酬になったりして、関係がこじれてしまうリスクがあります。
その点、弁護士は、客観的な立場から法的根拠に基づいて状況を整理し主張を行うため、感情的な対立を防ぐことが可能です。また、判例・裁判例や過去の類似事例を踏まえた現実的な解決案を提示することで、双方が納得できる着地点を見いだしやすくなります。
このように、早い段階から弁護士が対応をすることで、問題が大きくなる前に適切な解決を図ることができると期待できます。
お問い合わせください。
5、まとめ
残業代を請求された場合には、まずは従業員の主張に反論できるポイントがないかを確認することが重要となります。金額の算定方法や対象期間の確定など、専門的な判断が必要な事項も多いため、弁護士に相談するようにしましょう。
労働問題に詳しい弁護士に相談することで、トラブルが大きくなる前に解決できる可能性もあります。ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスには、残業代トラブルの解決実績のある弁護士が在籍しておりますので、ぜひご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています